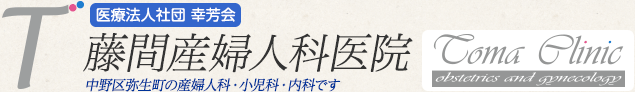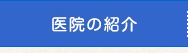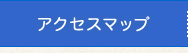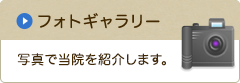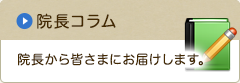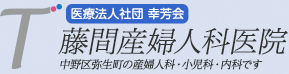カルテの余白
第5回「検診離れで増える子宮頸がん」(平成15年11月29日)
忘れられない患者がいる。大学病院で勤務していたときのこと。彼女は24歳。私が担当医になったとき、すでに子宮頸がんの末期だった。
最期を迎えるまでの半年、生い立ちや病気がちの子どものことをよく話した。子どもの看病で自らの治療が遅れたことも打ち明けてくれた。それでも、どうしてもっと早く受診を……いまでもそう思わずにはいられない。
子宮頸がんが増えている。それも、若い人に目立っている。厚生労働省の子宮頸がん検診の有効性評価に関する研究では、30歳以上を対象とした検診(細胞診)は「有効」だという。確かに90年代初めまでは受診者は増加し、死亡率も低下した。しかし、その後は受診率が低下し、死亡率が再上昇する事態になっている。
背景にあるのは、受診者の固定・高齢化と30~40代の検診離れだ。米国では2~3年の間に80%以上の女性ががん検診を受診(18~44歳は89%)するのに対し、日本では14%程度に過ぎない。それが、受診者からがんはわずかしか発見されず、受診しない若い人に発病が多いという結果を招いている。
欧米でも若い人の子宮頸がんが増えている。これは子宮頸がんにかかわるヒト乳頭腫ウイルス(HPV)に感染する機会が、性交渉の低年齢化や性パートナーの増加とともに増えているという事実による。米対がん協会は初めての性交渉後3年もしくは21歳を過ぎたら受診するべきだとしている。早く治療できれば、死亡率の減少のみならず、子どもを産めるような治療法を選ぶことも期待できる。少なくとも25歳から始めれば、その可能性はかなり高くなる。若い人の受診をいかにして勧めるか。日本でも早急に考えなければならない。